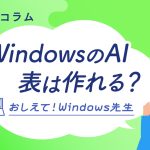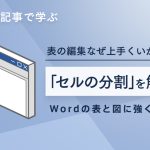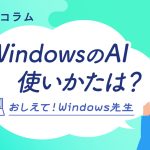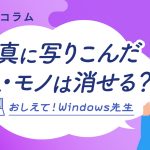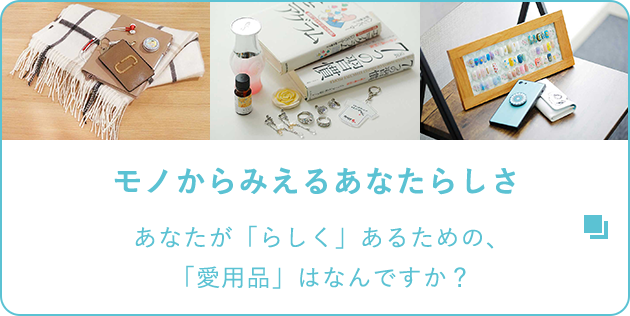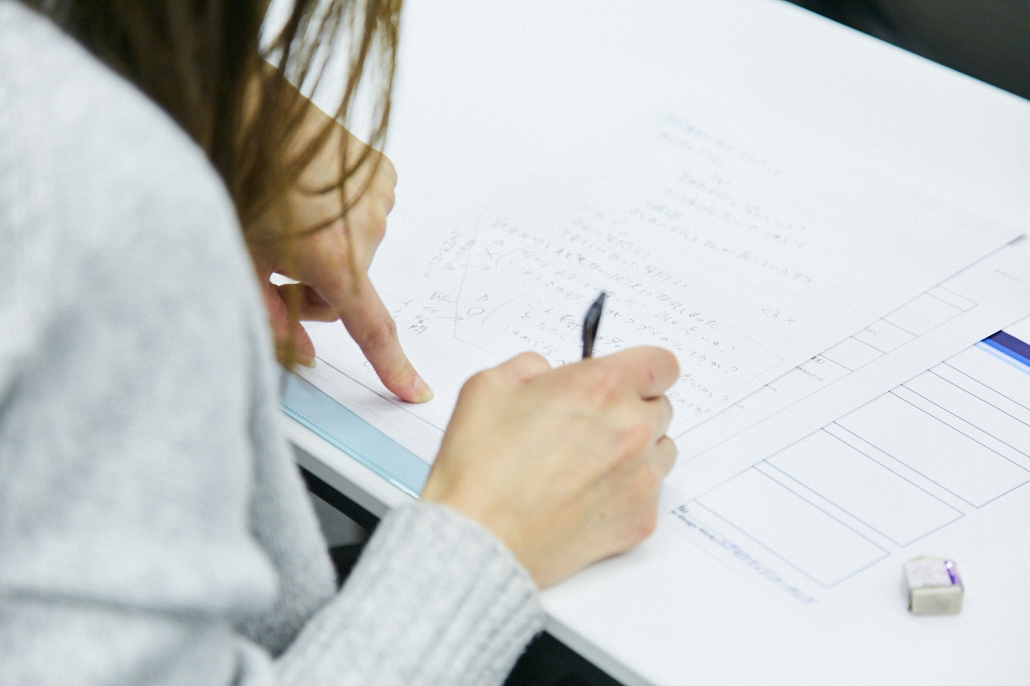
自分が一生懸命に取り組んでいることは、本当に求めていることなのだろうか?今ここで立ち止まって、そんなことを考えてみては?日々の習慣としてはもちろん、ときどきでも、問いの力を借りることで、本質が見えてくるのだという。今回紹介するのは、2月に開催された、「問い」の大切さを知るイベント。ワークショップでは、体感として問いの力を知ることにもつながった。

できるだけ「いい問い」を使う
講師の大嶋さんの仕事はコーチング。「コーチとはどんな仕事をすると思いますか?」と参加者に投げかける。アドバイスをしたり、ノウハウを教えたりすることもあるものの、一番は「問いを立てる」だそう。
コーチとは、クライアントの問題解決や達成したい夢を達成できるようにサポートする存在。そのときに、いい「問い」を投げかけると、クライアントはその問いの答えを探す過程で、自らの考えを見つけ、腑に落ち、自ら行動する。
大嶋さんは過去にコンサルタントとしてさまざまな提案をしてきたが、実行されるものが数少ないと感じていたという。それは、クライアント自身が心から納得できるレベルまで、提案が落とし込まれていなかったからだと気付いた。現在、コーチとして問いかけ、クライアント自身が答えを見つけることで、実行の可能性は飛躍的に高まったそうだ。
ここで、参加者に問いかける。
「あなたが今やるべきことは何ですか?」
スクリーンにそう映し出されるだけで、心の中で「私がやるべきこと……」と考えてしまう。それが問いの力だと大嶋さんは言う。

再度、問いを投げかける。
「あなたが今フォーカスすべき最も重要なことは何ですか?」
「先ほどの問いと比較してどうでしょうか?こちらの問いのほうがより『刺さる』人が多いんです。『自分にとって重要なこと』をつい考えてしまうから、こちらの方がより『いい問い』だと言えます」
なぜ、こちらの問いの方がいいのか?それは、重要という言葉が入ることで、そもそも自分にとって、重要なことは何だろうと、考えを深める問いだからだと、大嶋さんは説明する。
実際に、問いの答えを手元の用紙に書いてもらう。内容を確認すると「欲求が具体的になった」という意見や、「普段考えていることより、重要なことに気が付いた」という意見も。大嶋さん自身も、問いの力で、そのとき何を一番大切に思っているかに気が付いた経験がある。
自分の持って生まれた才能を知る

仕事で輝いている人や成果を出している人は、自分に対する問いの量が多い。必ず自分を振り返り、「何を学んだのか?」「この1年は自分にとってどうだったか?」「自分はどうなりたいのか?」を振り返る。また、彼らは自分の持って生まれた才能を理解し、才能を活用して価値を生み出している。
「しかし、『自分の価値は何なのか?』と、ギフトとも呼ばれる『持って生まれた』才能をわかっている人はなかなか少ないものです。SNSの影響もあり、周りと比較して自分を卑下してしまいがち。でも、誰でもオンリーワンなんです。その価値を知るには、次の問いが有効です」
「神様がいるとしたら、私にどんな才能を授けてくれたのか?」
参加者に考えてもらったところ「自分の価値や才能があるかもしれない」と再発見できた人も。自分に「いい問い」を投げかけるだけで、違った一面が見えてくる。
ケーススタディから知る「いい問い」

営業がうまくいかない人がいたとして、自分にどんな問いを投げかけるケースがあるだろう? 次のような例で示した。
Aさん「売り方が悪いのかな?」
Bさん「そもそも、相手は何を望んでいるんだろう?」
「ここでは、Bさんのように問いを立てられる人がこの後の成果を出します。一つひとつはちょっとした差でも、毎日の積み重ねで1年経てば大きな差になってしまうんです。Bさんのような問いを立てられるようになってもらいたいと思います」
また、トラブルがあったときにも、問いの投げかけ方で展開が変わってしまう。
Aさん
「どうしてこんなことになったのだろう?」
「誰が悪いのか?」
「いつまでこの状況が続くのか?」
Bさん
「これを何かのチャンスにできないか」
「どうしたらこの状況から前に進めるのか?」
「これから学べることは何か?」
「Bさんの問いのように、嫌なことがあっても、ポジティブに考える癖をつけておきましょう。人生には大変なことや、思い通りにならないことが多いものです。そんなときにどんな問いを自分に投げかけるのかで、その後が変わってきます」(大嶋さん)
ペアワークで新しい自分を発見する

ほかにもいくつかのポイントを示した後、最後にペアワークの時間が取られた。隣に座っている人同士で、お互いに10分ずつ質問をし合う。その時の質問するポイントは、できるだけ問いを短くすること。
また、自分の判断や価値観を脇に置いて、相手の話を無邪気に聴くことが大切になる。考えても見なかったアイデアや深く考えることを促すのがいい問いであり、そのような問いは、無邪気な姿勢から生まれる。そしていい問いは短い。
今回行った、問いを使った問題解決ペアワークは、ペアを組んだ人からの問いにより、自分の真の問題を明確にすることができると、大嶋さんは言う。
ステップ1
「解決したい問題は何か?」という問いをもとに、それぞれ自分の解決したい問題を考えて、紙に書く。
ステップ2
「そもそも本当の問題は何か?」「そもそも何が問題なのか」「どこに問題があるのか?」とお互いに問いかける。
問いかけのポイントは、紙に書いた問題が本当の問題なのか、何が本当の問題なのか、考えを深めること。そして、本当の問題を見つけ、その解決策を見つけることだ。問いを使って真の問題を明確にする、効果的な方法であると大嶋さんは言う。
お互いの問いかけが終わった後に、大嶋さんからの「気になった問題が変化した方はいますか?」という問いには多くの人が手を挙げた。

次に「真の問題は何か?」の問いに答えを書き、その後で「達成ないし達成された時のゴールイメージは?」の問いにも答えた。さらに、自宅に戻ってから「達成または、解決するための計画は?」の問いも考えてほしいと宿題も出された。
いい問いによって、問題の根本を探求していくことが大切。
「初めに問題だと思っていたことをすぐに解決しようとすると、間違ってしまうことがあります。なぜなら、問題だと思っていることが、実は、別の問題が原因で発生している問題で、本当の問題とは限らないからです。まずは、深呼吸をして、いい問いを使って、『なにが本当の問題なんだろう?』と自問自答して、本当の問題を見つけることが大切。また、いい問いをしてくれて、相談できる人を持つといいと思います」
改めて、問いを使って自分について見つめることで、本当の問題や解決方法、自分の価値なども見えてきたのではないか?
いい問いの仕方を身に着けて、毎日をより良い方向に向けていけるといい。
カメラマン:坂脇 卓也(さかわき たくや)