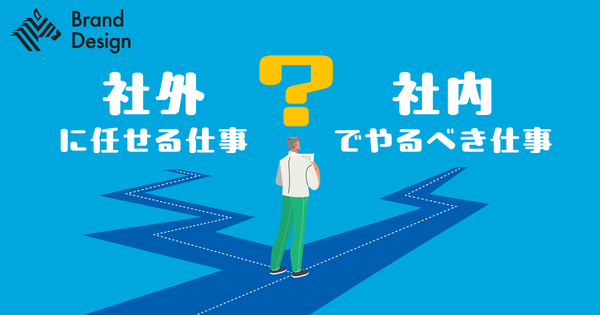属人的で自動化もできない仕事、効率化する方法は
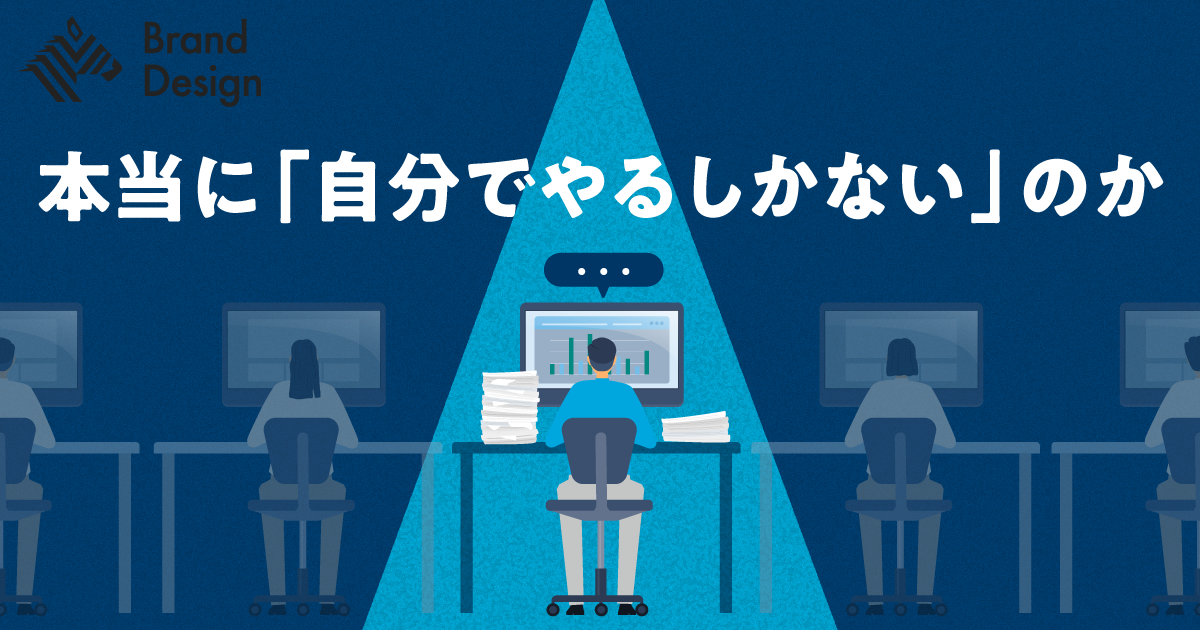
私たちの仕事には、大別して2種類がある。事業成長の核となる「コア業務」と、事業戦略に直結しない「ノンコア業務」だ。 「社員はコア業務に集中し、ノンコア業務はデジタルツールなどを導入して効率化すべき」というのが定石だが、思い返してみてほしい。 ノンコア業務の中で、自動化もできず、マニュアル化もしにくいため、人に任せることもできず、「これは自分でやるしかないな」と諦めている仕事があるのではないだろうか。 そんな「非IT×非定型」とも呼ぶべき業務の効率化に強みを持つのが、リクルートスタッフィングのBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)だ。 具体的にどのような活用事例があるのか。その結果、どれほど企業の生産性は上がったのか。BPOソリューション営業部の野々山岳氏に話を聞いた。
効率化されない「非IT×非定型」業務
ノンコア業務を効率化して、生産性を高めよう。
組織としてこのような決断をすると、ツールを活用した業務の自動化やDX促進、事務処理業務におけるBPOなどの導入を検討されることが多い。
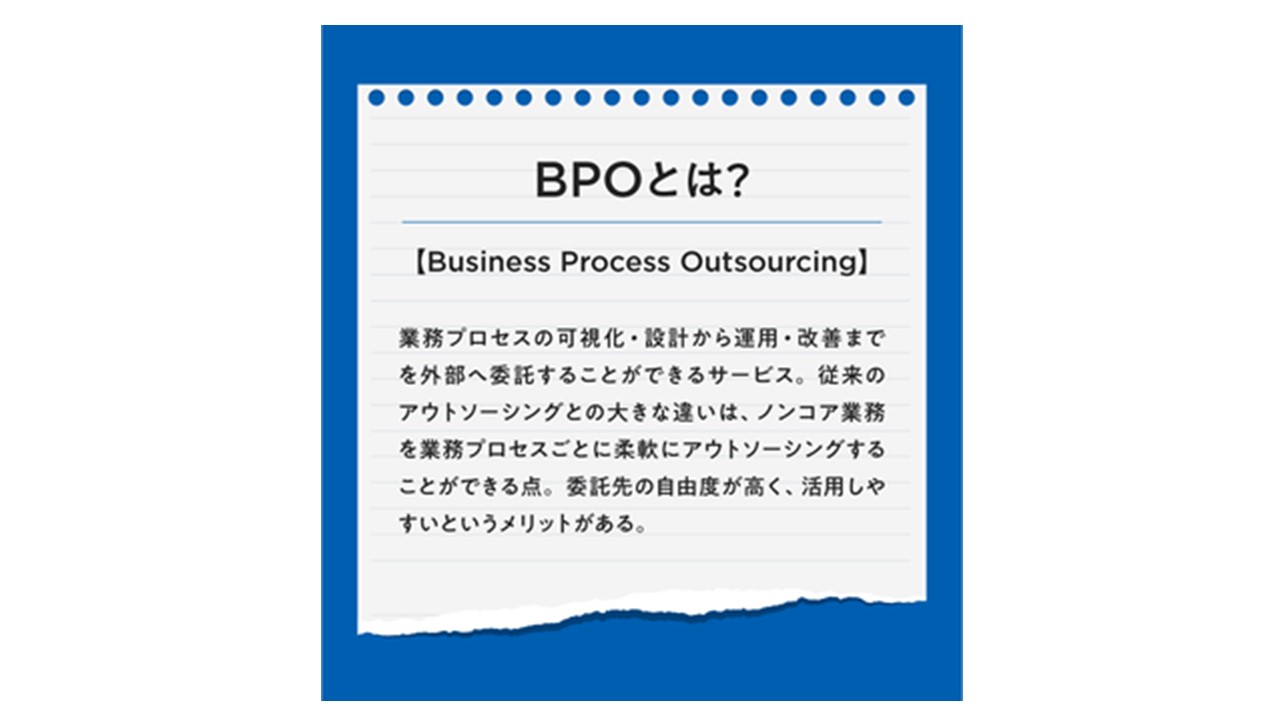
では、それで全員がコア業務に集中できるかといえば、答えはNoだ。BPOサービスを提供するリクルートスタッフィング BPOソリューション営業部の野々山岳氏は、「非IT業務の効率化には手付かずの企業も多い」と話す。
「非IT業務には2種類あり、コールセンターや金融機関における事務センターが担う『定型』的な業務は、マニュアル化しやすく、アウトソーシングもしやすい。非IT分野で効率化から取り残されやすいのは、『非定型』の業務です」(野々山氏)

非定型業務とは、人事、購買、経理、総務等のコーポレート関連(管理系)業務。あるいは、現場に近い受発注の事務や、アシスタント等の営業バックオフィス関連業務などが含まれる。
これらの非定型業務の効率化が進まない背景としては、
・「何十年もAさんだけがやってきた」業務の属人化
・「B社は受注時の業務フローが異なる」「月初に請求書を送付する決まりだけど、C社だけは月末で」などの取引先ごとの個別対応などが挙げられる。
「ああ、あれだな」と、思い当たるふしがある人も多いだろう。
コロナ禍を経て、定型業務ではAIチャットボットに代表されるようなツールの導入や自動化が進んだ。一方で「自動化もできず(非IT)、マニュアル対応もできない(非定型)業務」が顕在化したケースもあるという。

「BPOベンダーも、『非IT×非定型』の業務を積極的に受け入れない傾向があります」と、野々山氏。
非定型業務は担当者のスキルや知識に依存するため、社外に切り出すためには、業務内容を明確にし、標準的な手順にする必要がある。しかし、そもそもの業務が複雑なので、中途半端に手を入れてもいい結果にはならない。
つまり、非IT×非定型業務の効率化は、組織にとってもBPOベンダーにとってもハードルが高いのだ。
「それまでの慣習やお取引ルールで残っている個別対応は、一般的なBPOで依頼できる定型業務ではありません。そのため、効率化したいと思いながらも、社内で対応し続けているケースが多いのです」(野々山氏)
組織全体としての生産性向上のカギは、非IT×非定型業務にあるといえそうだ。
業務を可視化するプロの手腕とは
先ほど、「非IT×非定型業務の効率化には企業もBPOベンダーも消極的」と伝えたが、ひとつ訂正がある。リクルートスタッフィングは非IT×非定型業務の効率化に積極的だ。
これまでにも多くの企業の非IT×非定型業務にテコを入れ、生産性向上という結果を出してきた。むしろ、強みと言ってもいいだろう。
「まだBPOというサービスが認知されていないこともあり、私の肌感ではお問い合わせの5~6割くらいが『課題があるが、BPOが最適なのかどうかわからない』という方です」と、野々山氏。
リクルートスタッフィングでは、BPOサービスだけでなく、派遣や自動化ツールなどの選択肢も提示できるため、その粒度での相談でもまったく問題ないのだという。そこからは、効率化のプロとしての腕の見せどころだ。
「私たちは、事前のヒアリングで見えてきた課題を踏まえて業務調査を行い、業務を洗い出し、可視化することからはじめます。

調査の過程で、ぼんやりしていた課題がはっきりしますし、目詰まりしている箇所も見つかる。それをもとに、BPO化のメリットはもちろん、業務の企画・設計から実働まで、プロセス全体のアウトソーシングをオーダーメイドでご提案します」(野々山氏)
場合によっては、BPOではなく、「派遣社員に来てもらったほうがいい」「ツール導入で解決できそうだ」という結論に至ることもあるという。
では、どのようにオーダーメイドなBPOを提案するのか。たとえば、機械部品の受注に関わる事務処理や管理を担っていた、とあるBtoB企業の10人ほどのチームの場合。メンバーの高齢化によって、そのチームの人員は1年以内に半分になることが決まっていた。
言い換えれば、10年選手、20年選手というベテラン揃いのチームだったわけで、自動化やアウトソーシングをためらうのも無理はない。しかし、仕事が回らなくなる未来も見えている。そこで、リクルートスタッフィングに相談があったのだ。

「業務調査によって業務を可視化するのに、通常は1か月ほどかかりますが、このケースではベテランの方々の膨大な脳内データをアウトプットしてもらう必要があったため、2か月ほどかけて実施しました」と、野々山氏。
次のステップは、洗い出した業務を整理し、ドキュメント化して、「こんな業務がある」「こんなバリエーションがある」「だから、こういうルールを定めてはどうか」と企業に提案することだ。ここに、「非IT×非定型」業務を効率化する大切なポイントがある。
「私たちは、ルールを統一してすべてのケースに無理やり当てはめるのではなく、『それぞれの対応に必要なルールを決める』という方針です。基本的な業務プロセスは共通化しながら、取引先ごとのルールなど必要不可欠な対応は、バリエーションとして整理します」(野々山氏)
「ルールに当てはめられないから」と効率化から取り残されるよりは、多少工数が増えても必要なことは個別対応する。そうすることで、組織全体の生産性を高めていくのだ。
BPOで業務はブラックボックス化するのか
このようにして、2か月ほどかけてBPOの内容について合意形成し、業務調査開始から約4か月ほどで運用が開始されたという。
「BPOのチームは類似業務の経験者を採用しながら体制を構築し、徐々に業務をスイッチさせていくという段階を踏みました。運用開始から安定して稼働するまで、だいたい半年程度かかりました」(野々山氏)
安定稼働以降のBPOチームの教育に関しては、リクルートスタッフィング側が担うため、組織は教育コストをかけることなくコア業務に集中することができる。BPOによって、ある組織が救われたのだ。
これは間違いなく成功事例だが、業務プロセス全体を任せられるというBPOの安心感は、「必要な知見が内部に蓄積できず、ブラックボックス化してしまうのでは」という不安と表裏一体でもある。

これに対して野々山氏は、「お客様からよく聞く懸念のひとつです」と話す。
「私たちはBPOサービスだけを提供しているわけではないとお話ししました。お客様、そして事業ごとに目指す方向があり、解決したい課題があるなかで、どのような手段がもっとも生産性向上に寄与するかを常に考えることが私たちの使命です。
そういう意味では、単純な外注ではなく、伴走のような側面もあります。
業務のブラックボックス化は、お客様の事業成長を考えても、決して良いことではない。そこで、定量的なデータだけでなく、業務課題や利用顧客のご意見など定性的な事象も含めて月次でご報告しています」(野々山氏)
たとえば、マニュアルひとつ取っても、一度作って完了ではなく、常にアップデートしていく。その「最新版」を、BPOチームだけでなくクライアントも見られる場所に置いておく。

考えてみれば、「非IT×非定型」業務は、担当者の脳内だけにルールがあり、ブラックボックス化していた可能性が高い業務だ。そのマニュアルが作られるだけでも効率化の観点では大いなる進歩であり、組織にとっては知見を蓄積する土壌づくりになる。
業務を「投げっぱなし」の企業と「受けっぱなし」のBPOベンダーであれば、ブラックボックス化してしまう可能性もあるが、上記のような対応方針であれば、導入以前よりもむしろ知見は貯まりやすくなると言えそうだ。
「伴走するBPO」とは何か
人手不足、働き方改革などを背景に、BPO市場全体に対する需要も高まっているが、リクルートスタッフィングもその例外ではない。難易度の高い「非IT×非定型」業務の効率化を次々に解決してきた実績も相まって、多くの企業が相談に訪れ、導入に踏み切っている。
多くのBPOベンダーがあるなかで、なぜリクルートスタッフィングが選ばれるのか。
野々山氏は、「派遣やBPOの導入によってすでに関係性がある企業様も多い」と前置きしたうえで、「伴走する、という意識でしょうか」と答える。
たとえば、業務の運用を継続し、標準化を進めることで、人手を介さずに対応可能な業務が見えてきたとする。
そうしたケースでは、「一部を自動化することで、業務工数を減らしましょう」と、あえて自社にとってのマイナスの提案することもあるという。業務量が減少すればBPOチームの売上は減ってしまうが、クライアントにとって、プラスだからだ。

そうした誠実な対応も功を奏し、「ありがたいことに、ある部門の業務をBPOとして運用していく過程で、ほかの部門からも声をかけていただくケースが多くあります」と、野々山氏。
煩雑だが、コアではない業務に、それだけ多くの人や部門、企業が悩まされているということだろう。そして、BPOがひとつの解になるという確信が野々山氏にはある。
「少し大きな話をすると、2025年問題にあるように労働人口減少や高齢化が進み、より一層さまざまな年代の方が活躍する社会になるでしょう。
そのような状況で社員に何の業務を担ってもらうかは、企業にとって非常に重要なテーマだと思っています。社員さんには、やはり核となる『コア業務』に集中してほしい。
これまで社員の方お一人おひとりが培ってきた知見・経験値をもとに、ナレッジを展開してもらったり、若手の育成に携わってもらったりすれば、企業だけでなく日本全体の未来も明るくなる。
『任された仕事だけやる』のではなく、企業全体の生産性を高めるための提案と確実な運用を通じて、社会全体に利益を還元できる。BPOはそれだけの可能性があるサービスだと感じています」(野々山氏)
執筆:唐仁原俊博
撮影:小島マサヒロ
デザイン:高木菜々子
編集:大高志帆
NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。
202︎5-︎︎3-12 NewsPicks Brand Design