事務BPOとは|注目される背景や依頼できる業務
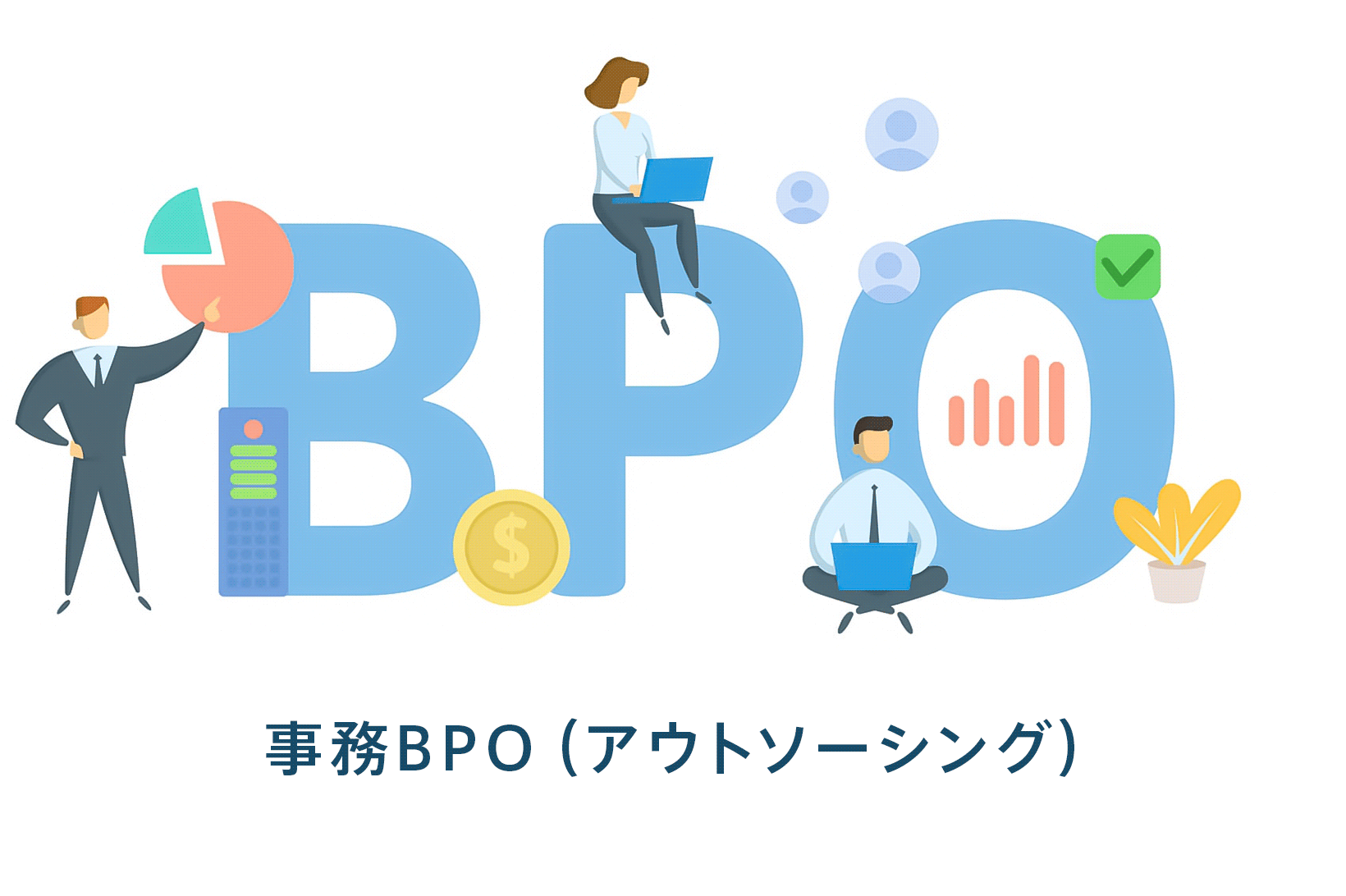
人材不足を補填するサービスのひとつに事務BPOがあり、活用することで業務の効率化やコスト削減、専門知識を持つ人材の確保といった課題の解決が可能です。しかし、導入にあたっては契約形態やセキュリティ対策など、注意すべき点もあります。どの程度の規模から依頼が可能なのか、どういった契約形態が適しているのか、悩むケースもあるでしょう。 この記事では、事務BPOの概要、注目される背景、依頼できる業務の種類、導入のメリットや注意点について解説します。
目次
事務BPOとは
事務BPO(Business Process Outsourcing)とは、財務や経理、人事といった、企業の根幹を担う事務業務の一部または全部を外部の受託企業に委託することを指します。
企業が事務BPOを導入する目的には、業務の効率化と負担軽減が挙げられるでしょう。特に、事務業務には定型的な作業が多く、外部委託することでより重要な業務に専念できる環境を整えられます。業務効率や生産性向上などが期待でき、専門的な知識が必要な業務については、BPO受託企業が対応することで品質の向上も見込めます。
アウトソーシングとの違い
BPOと混同されがちなものに、「アウトソーシング」があります。BPOはアウトソーシングの一種ですが、別のものとして考えられるようになってきました。
アウトソーシングは特定の業務を外部に委託することを指し、単純な作業の外注が中心です。それに対してBPOは、業務の設計や改善も含めて外部委託し、業務プロセス全体の最適化を目的とする点が特徴です。
つまり、BPOは単なる業務の外注ではなく、業務プロセスの最適化を含めた包括的なサービスとなります。
BPOが注目される背景
BPOの市場は事務分野に限らず年々拡大しており、多くの企業が導入を進めています。その背景には、働き方改革や人材不足といった社会的要因が大きく関係しています。
働き方改革による業務効率化のニーズ
企業は働き方改革の推進により、長時間労働の是正や業務効率化を求められています。しかし、社内のリソースだけで業務を見直し、改善するのは容易ではありません。そこで、BPOを活用することで、業務フローを整理し、より生産性の高い働き方を実現する企業が増えています。
人手不足の深刻化
少子高齢化による労働力不足は、企業にとって大きな課題となっています。バックオフィス業務でも人材の確保が難しく、採用・教育のコストも増加しています。事務BPOを活用すれば、専門スキルを持つ外部の人材を活用できるため、自社での人材確保の負担が軽減できます。
事務BPOで依頼できる業務
事務BPOでは、企業のバックオフィス業務を中心に幅広い業務を委託できます。単純なデータ入力業務から、専門的な知識が必要な業務まで対応可能で、企業のニーズに応じた柔軟な運用が可能です。
<依頼できる主な業務>
・経理:請求書処理、支払い管理、会計データ入力など
・人事・労務:給与計算、社会保険手続き、勤怠管理など
・採用(RPO):採用活動の計画・実施、応募者管理、面接調整など
・総務・受付:備品管理、社内イベント運営、来客対応など
・購買:仕入れ業務、発注・在庫管理など
・営業アシスタント:営業資料の作成、データ入力、顧客対応など
・受発注管理:注文処理、納期調整、在庫管理など
・コンタクトセンター業務:カスタマーサポート、コールセンター対応、メール対応など
・制作・編集アシスタント:記事やコンテンツの編集・校正、データ入力など
・学校事務:学生情報管理、授業運営サポート、入試関連業務など
・事務局運営:イベントやプロジェクトの事務局運営、問い合わせ対応など
・金融事務:融資業務、口座管理、保険手続きなど
・貿易事務:輸出入手続き、通関書類作成、海外取引先との調整など
<関連記事>
RPO(採用代行)とは|委託可能業務や導入のメリット
事務業務でBPOを利用するメリット
事務BPOを導入することで、企業は業務効率の向上やコスト削減など、さまざまなメリットを得られます。事務BPOを利用するおもなメリットを紹介します。
専門知識が必要な業務に対応しやすい
事務BPOを活用すれば、専門知識を必要とする業務をBPOスタッフに任せられます。
事務業務のなかには、頻繁に法律や制度が変更される分野があります。たとえば、労務・人事や経理などは、最新の法改正に対応する必要があり、社内で専門知識を持つ人材を確保したり、業務に対応できる人物を育成したりするのは負担が大きいでしょう。事務BPOの利用によって、専門知識を持つスタッフに業務を任せることができ、社内での対応コストの削減が可能です。
業務効率化が実現できる
事務BPOを活用することで業務プロセス全体の見直しが可能です。
定型業務の多い事務業務は、効率化の余地が大きい分野ですが、現場では社員が自分の裁量で業務を進めてしまったり、業務改善に取り組む時間が確保できなかったりと、非効率なまま運用されているケースもあります。事務BPOを導入する際は、受託企業が業務調査のうえ業務設計をおこなうため、業務の標準化や自動化が進みます。
コア業務へ集中できる
事務BPOを導入することで、社員がより付加価値の高い業務に専念できるでしょう。企業の競争力を高めるためにはコア業務に注力することが重要ですが、事務業務に多くのリソースを割けば、肝心の戦略的業務に十分な時間を確保できません。
事務BPOを導入すると、自社でおこなうべき業務、委託可能な業務が切り分けられ、コア業務に集中できる環境を整えられます。
業務品質が向上する
事務BPOを利用すると、自社で遂行するよりも、業務品質の維持や向上がしやすくなります。 BPOの受託企業は、事務業務の専門的なノウハウを持ち、業務の標準化や品質管理の体制が整っているため、正確性やスピードを向上させることが可能になるのです。
属人化の解消・防止できる
事務BPOを導入すれば、属人化を防ぐことができます。事務業務の属人化は、多くの企業が抱える課題のひとつです。特定の担当者がいなければ業務が進まない状況では、引き継ぎの負担が大きくなったり、業務が停滞したりする可能性があります。BPOの受託企業が業務設計の際にフローを整理し、可視化を進めることで、属人化が解消できるでしょう。
事務BPOの導入の注意点
事務BPOには多くのメリットがありますが、導入に際しては社内でのスキルの蓄積や、セキュリティリスクなど注意すべき点もあります。適切に事務BPOを運用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
スキルや知識が社内に蓄積されにくい
事務BPOを利用すると、業務の遂行自体はスムーズになりますが、自社内にノウハウが蓄積されにくくなるというデメリットがあります。特に、業務を完全に外部委託してしまうと、担当者の入れ替わりや契約終了後に問題が発生する懸念があるでしょう。受託企業から提出された業務マニュアルを確認し、定例報告会で業務の進捗や課題を把握することが重要です。
セキュリティリスクの管理
事務BPOでは、社内の重要なデータや個人情報を外部に提供することになるため、情報漏えいやセキュリティリスクに十分な注意が必要です。
BPO受託企業がプライバシーマークなどセキュリティ認証を取得しているか確認し、契約時はデータの取り扱いやアクセス権限について明確にしておきましょう。定期的に監査し、情報管理が適切かチェックすることも重要です。
コストの見極め
事務BPOを利用することでコスト削減が期待できますが、契約の範囲を適切に設定しないと、想定以上のコストがかかることもあるため、事前に十分な検討が必要です。
依頼する業務の範囲を明確にすることで、不要なコストの抑制につながります。初期費用・運用コスト・追加費用などは、どのような内容が含まれているのかしっかり確認しましょう。短期的なコスト削減だけでなく、中長期的なコストパフォーマンスを考慮することも重要です。
事務BPOの契約形態
事務BPOを導入する際には、契約形態を理解し、業務の責任範囲を明確にすることが重要です。契約形態には主に「委任契約・準委任契約」と「請負契約」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
委任契約・準委任契約
委任契約・準委任契約は、依頼する業務の「遂行」が目的であり、成果物の完成を保証するものではありません。BPO受託企業は業務を適切におこなう「善管注意義務」を負い、継続的な業務を依頼したい場合や、業務の遂行自体が重要で、成果物の有無にこだわらない場合に適しています。
カスタマーサポート業務、事務局運営、経理処理のサポートなどでよく利用されています。
請負契約
請負契約は、依頼した業務の「成果物の完成」が目的であり、BPO受託企業は成果物の品質や納期を保証する義務があります。明確な納品物や成果が求められる業務や、品質や納期の保証を重視する場合に適しており、決算書の作成やデータ入力業務などでよく利用されます。
契約形態の選び方
事務BPOを導入する際は、業務の性質や目的に応じて契約形態を選ぶことが重要です。業務プロセスの一部を長期的に委託する場合は「委任契約・準委任契約」が適しており、一方で特定の業務の成果物を求める場合は「請負契約」を選ぶのが一般的です。
契約時には責任範囲を明確にし、後々のトラブルを防ぐための取り決めをおこないましょう。
事務BPOについてのよくある質問
Q. 小人数・小規模でも依頼できますか?
A. BPOベンダーによって異なります。リクルートスタッフィングの場合、オフサイトであれば規模を問わず依頼が可能です。オンサイトであれば偽装請負を防止する観点から、3人月以上の業務量が必要となります。
Q. どういった業務が事務BPOに向いていますか?
A. 指揮命令が必要なく業務を遂行できるものであれば、業務委託が可能です。オフサイトとオンサイトそれぞれ適した業務があるので、事務BPOの受託企業に相談することをおすすめします。
Q. オンサイトBPOは可能ですか?
A. BPOベンダーによって異なります。発注した企業の社内に常駐する形で業務を遂行する「オンサイトBPO」を提供する企業もあります。
<関連記事>
オンサイトとオフサイトの違いとは?BPOの運用形態の特徴を解説
Q. 事務BPOはどういった会社に依頼すべきですか?
A. 受託企業ごとに得意とする分野が異なるため、依頼業務によって以下を参考に選ぶことをおすすめします。
定型的な業務で、業務ボリュームがある:自社センターを有し、ボリュームの高い業務を請け負うインフラ、場所などが潤沢に手配できる企業
定型的な業務で、業務ボリュームが少ない:3人程度からでも受託可能な小規模でも対応した実績のある企業
非定型的な業務で業務ボリュームがある:業務分析を得意とし、オンサイト対応ができる企業
非定型的な業務で業務ボリュームが少ない:業務分析を得意とし、小規模でも対応できる企業
リクルートスタッフィングは業務分析に強みを持ち、非定型的な業務のBPOも得意としています。委託する業務が整理できていない場合でも、業務調査によってBPOの業務を設計します。少人数のご依頼も可能なため、事務BPOを検討する場合はぜひご相談ください。
課題解決のために事務BPOの活用を検討しては
事務BPOは、企業のバックオフィス業務を外部に委託することで、業務効率の向上やコスト削減を実現できる手段です。特に、人手不足や働き方改革の影響を受ける企業にとって、業務の最適化や専門知識の活用ができる点は大きなメリットといえます。
BPOは適切な受託企業を選び、業務範囲や運用体制を明確にすることで、スムーズな導入が可能になります。自社の課題解決のために、事務BPOを活用しましょう。


