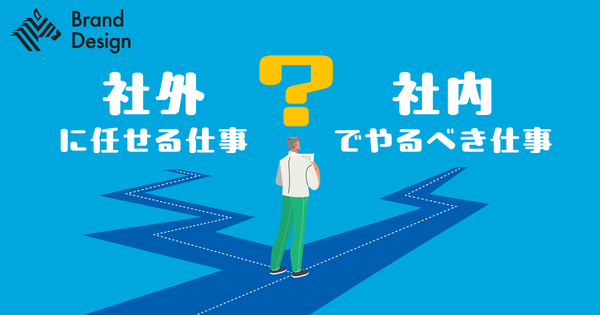リスキリングとは?新たな時代を生き抜く人材戦略

昨今、「リスキリング」という言葉への注目が高まっています。デジタル時代の到来による事業やサービスなどの急激な変化に対応するため、経済産業省が日本企業に対し、新たなスキルや知識の習得の必要性を提唱していることも要因の一つです。海外の企業では先進的に導入をし、新たな時代での経営戦略の一つとして人的資源である人材の育成・再教育が求められています。ここでは「リスキリング」について詳しく解説していきます。
リスキリングとは
リスキリング(Reskilling)とは、働き方の多様化や技術の進展などによる産業構造の根本的な変化によって、今後新たに発生する業種や職種に順応するための知識やスキルを習得することを目的に、人材の再教育や再開発をする取り組みを意味します。リスキリングという言葉は、日本ではまだなじみがない人も多いかもしれません。しかし、昨今の日本企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組みはじめたことをきっかけのひとつとして、日本でも必要性が高まっています。
リスキリングの定義
経済産業省はリスキリングの定義を「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」と定めており、リスキリングは社会人の転職やキャリアアップの場で多く用いられる傾向があります。
企業側も、厳しい競争のなかで生き残るために、既存の事業の付加価値を高める必要や新たな領域にチャレンジする必要があります。そのため、すべての従業員に、これからの職場で必要なスキルを習得してもらうための取り組みが大きな意味を持つようになります。リスキリング自体は海外の有名企業などが先行し、早期に着手している取り組みではありますが、近年の日本企業でもその必要性から導入に意欲的な企業も少なくありません。
リスキリングとリカレントの違い
リスキリングは、「リカレント」と同じ意味で使用される場合があります。「再教育、新たなスキルを身につける」という言葉の意味において違いはありませんが、主体が企業側になるのか労働者になるのかという部分が大きく異なります。
リスキリングは企業側がこれから必要となる知識やスキルを身につけてもらうために従業員に対して施す取り組みです。一方、リカレントは社会人が今の仕事で必要となる専門的知識やスキルを身につけたり、就業先を一度離れ、教育機関で学び直したりするなど、自らのライフスタイルに合わせた生き方や働き方を選ぶための手段として使われます。
リスキリングとアンラーニングの違い
アンラーニング(Unlearning)は「学習棄却」と訳され、これまで学んだことを棄却し、新たに学び直すことです。棄却といってもすべて捨て去るわけではなく、自身の持つ知識や価値観などを認識し、現状に合わなくなったものは捨て、新たに有効な知識やアイデアなどを取り入れることが重要とされています。
リスキリングとアンラーニングは同じ文脈で使われることがありますが、リスキリングが新たなスキルを身につけることを主目的とするのに対し、アンラーニングは過去を振り返って取捨選択することがポイントです。アンラーニングによって古くなった知識や価値観を整理することで、リスキリングがしやすくなります。
リスキリングが注目されている背景
リスキリングが注目されている背景は大きく分けて2点あげられます。それは、「デジタル時代の到来」と「コロナ禍による働き方の変化」です。とりわけ近年では、デジタル化によって新たに生まれる職業や職種、仕事の進め方など大幅な就業スタイルの変化に伴いスキル習得が必要になるケースが増えています。また、新型コロナウイルスの流行によりテレワークの推進や、対面ではなくオンラインでの顧客とのやり取りなど、既存の働き方では対応できないケースも増えています。逆に、人手が不要になった職種もあり、従業員も自らの活躍の場を創造していく必要があります。
このような環境変化に適応するため、新たな事業戦略として必要なリスキリングを進めていくことが企業に求められています。
2020年に開催されたダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)で、リスキリング革命(Reskilling Revolution)が発表されたことも、リスキリングが注目される理由です。
リスキリング革命では、2030年までの10年間に「10億人がリスキリングの機会を得る」という目標が掲げられました。これを目指して世界各国でさまざまな取り組みがおこなわれており、日本では2022年に、当時の内閣がリスキリング支援に5年で1兆円を投入する方針を発表しました。
同じく2020年に公表された、人材版伊藤レポート(持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書)で取り上げられたことも、リスキリングが注目されたきっかけでしょう。人材版伊藤レポートは、経済産業省が主導する「人的資本経営の実現に向けた検討会」が取りまとめた報告書です。急速な技術革新やビジネス環境の変化に対応するために策定されたガイドラインであり、そのなかで言及されたことで、リスキリングの重要性があらためて認識されました。
日本企業にとってのリスキリング
日本企業にとってのリスキリングはデジタル化の推進に伴う、人事戦略の一つとして欠かせないものになると考えられます。リスキリングは、既存の組織や業務を推進することを前提とするのではなく、現存しない組織や業務を遂行するために必要な人材の育成を目指すものです。
日本企業においての教育プログラムとして、「OJT(職場内教育訓練)」という既存の組織や業務を対象とした取り組みがありますが、リスキリングはOJTと違い、新しいビジネスモデルの開発や新たな付加価値の高い商品・サービスの創出のために重要な要素となります。そのため、今後必要となるスキルや能力が足りていない人材をリスキリングすることで、変化するビジネスモデルや事業戦略に対応できる人材へと再教育する企業が多いようです。
リスキリングは日本政府でも推奨しており、企業に向けたさまざまなリスキリング支援事業がおこなわれています。たとえば厚生労働省では、企業が従業員のスキルアップを目的とした教育訓練を実施する際に、「人材開発支援助成金」として費用の一部を補助する事業を展開しています。
また、同じく厚生労働省が実施する「特定求職者雇用開発助成金」、経済産業省が実施する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」などのほか、自治体でも助成制度を設けている場合があります。
リスキリングが企業にもたらすメリット
リスキリングが企業にもたらすメリットはさまざまです。とくに近年では、デジタル化において新しく生まれた業種や職種への人材投資として、企業に大きな影響を与えています。また、新型コロナウイルスによる環境変化に伴い、デジタルでのサービス提供やモノづくりへの関心が高まったこともあり、飛躍的に需要が高まりました。ここでは大きく4つのメリットについて解説していきます。
新しいアイデアの創出
リスキリングを行うことにより、従業員が新しいスキルや知識を習得することで、従来にはなかったアイデアが社内から生まれやすくなります。リスキリングは、時代の流れや産業構造の変化に伴う既存の事業の衰退や陳腐化を防ぐと同時に、新規事業やサービスを生み出すことによって売り上げの拡大、あるいは経営改善に役立てることができます。さらに、法的な枠組みの変化、新技術や競合の台頭など、様々な変化に対し、適応性の高い戦略を描き直すことができます。つまり、新しい戦略に合わせ、組織機能の変革や新規リソースの獲得など柔軟に対応することができるようになるのです。既存新規に関わらず、社内に新しい風を吹き込むという面においてもリスキリングを行う価値は高いと言えるでしょう。
業務効率化、生産性向上
リスキリングへの取り組みは、習得したスキルや知識を既存の業務の効率化に活かすこともできます。とくにデジタル化の推進で業務の自動化や工数の削減をすることで、本来専念するべきであるコア業務や新規事業の設立に伴う新しい業務へ今まで以上の時間を割くことができます。そのため、個人の生産性の向上やスキルアップによる更なる業務効率化が期待できます。つまり、企業側は既存の人材を今まで以上に有効活用することができるのです。従業員側も雇用が安定することはもちろん、今までの業務に加え、新たなスキルや知識の活用でより企業側に貢献することができます。リスキリングは、デジタル時代において企業側と従業員個人の双方が生き残っていくための人事戦略だと考えられています。
企業文化の継承
これまで企業が積み上げてきた独自の企業文化や社風などを守ることもリスキリングの大きなメリットの一つと言えるでしょう。これまで社内で活躍してきてくれていた人材のリスキリングによって、既存の従業員を解雇して新たな人材と入れ替える必要がなくなります。つまり、既存の従業員が今まで作り上げてきた文化を継承するかたちで、自社の強みや優位性を生かした戦略をたてることができます。新規のものを取り入れることも手段としては有効ですが、既存の事業や文化とバランスよく融合させることは簡単なことではありません。そのため、既存の従業員のリスキリングに取り組むことは、新しい事業などを軌道に乗せるうえでも有効な手段となるのです。
採用コストの削減
既存の社内人材をリスキリングし活用することにより採用コストを削減することもできます。新たなスキルや知識を持つ新規の人材を社外から即戦力として採用しようとすると、採用費用のみならず育成などにも大幅にコストがかかります。労働人口も減少するなか、新規の人材に頼るだけではなく、既存の人材をリスキリングし異動させるなどの施策で経費を抑えることができます。そして、新たな利益を創出することのできる分野や事業へ従業員を戦力化をしていくことが、リスキリングの上手な活用法だと言えるでしょう。
自律型人材の育成
リスキリングに取り組むことで、自律型人材を育成する環境づくりにつながります。自律型人材は、業務の意義や意味を理解して、指示を待たすに能動的に行動できる人材を指し、変化の激しいビジネス環境で求められる人材です。
リスキリングを推進することで、従業員にもみずから新しい知識やスキルを学ぶ意識が生まれるでしょう。自発的に学ぶ意思と環境がそろうことで、自立型人材の育成が期待できます。
リスキリング実践のステップ
リスキリングの導入にはいくつかのステップがあります。前提として、リスキリングの価値を従業員自身に理解してもらい、継続できるように支援することが大切です。社内人材が学び直し、学び続けることは、企業にとっても従業員個人にとっても長期的に生き残っていくために欠かせません。そのためには、学習自体への心理的ハードルを下げ、企業側も個人の学習進捗管理をするなども重要です。学習を離脱してしまう人が出ないように、全員で積極的に取り組む意識を大切にしましょう。
1. 理想とする人材像やスキルを設定する
自社の人材戦略にもとづき、その実現に必要な人材像やスキル、知識などを明確にします。事業に必要なスキルが社内になければ、それがリスキリングの対象となるでしょう。従業員の興味・関心だけでリスキリングを進めると、事業の成長にはつながらないかもしれません。人材戦略にもとづいた、理想とする人材像やスキル、知識などを従業員に提示すれば、リスキリングの指針や学習のモチベーションとすることができます。
2.リスキリングのプログラムを作成する
新しい業務に必要なスキルや知識と、現在従業員が保有しているスキルや知識のギャップを埋めるためのリスキリングのプログラムを作成します。自社で学習プログラムを開発する企業もありますが、企業によって適しているリスキリングのプログラムは各々異なります。そのため、外部のコンテンツやプラットフォーマーを活用するほうが、リスキリングを行ううえで質の高いプログラム構成を用意することができたり、リスキリングを行うまでにかかるコストや時間が削減できたりする可能性が高い場合もあります。大事なのは、リスキリングに取り組む従業員が、効率よくスキルや知識を習得できるプログラムを作成することです。
3.業務でスキルを実践する
リスキリングで習得したスキルや知識を「宝の持ち腐れ」にさせず定着させるために、実際の業務で実践する機会を提供します。まずはトライアルなど簡易的なものから、徐々に実践的なものへと移行していき、現在の業務にも応用が利くようにしていくのがスムーズでしょう。これにはリスキリングを主導する部署と現場がうまく連携して進めていくことがとても重要になります。リスキリングは、学習プログラムを提供し、受講してもらって完了ではありません。新しいスキルを獲得した人材が、新しい仕事で成果を生めるようになるところまでがリスキリングです。このステップは、プログラムの参加者へのリスキリングの効果を検証するプロセスにもなっています。
リスキリングで失敗しやすいケース
企業がリスキリングに取り組んでも、思うような成果が出ないケースもあります。
例えば、リスキリングが業務を圧迫して負担となり、従業員がリスキリングに良い印象を持たないこともあるでしょう。「無理にさせるのは良くない」と従業員の自主性に任せた結果、リスキリングが進まなかったり、モチベーションが低下したりする可能性もあります。
また、せっかくリスキリングをおこなっても、学んだスキルや知識を実践する場がなく、忘れられてしまったり、人材が社外に流出してしまったりといったリスクも懸念されます。
こういった失敗を防ぐためにも、事項でご紹介するリスキリングを実践するうえでのポイントを押さえておきましょう。
リスキリングを実践するうえでのポイント
リスキリングを実践するうえでのポイントもいくつかあります。リスキリングは継続して行うことが大切です。日本ではリスキリングの認知度がまだ低いこともあり、企業にとっては導入時の課題がいくつかあります。従業員へのヒアリングや学習理解度、利用ニーズなどに合わせて、企業側が従業員の学習を促進する仕掛けを構築していくことがとても重要です。従業員がリスキリングに取り組みたくなるような仕組みを設けるポイントを解説します。
社内の理解と協力体制を整える
まずは社内のリスキリングに対する理解と協力体制を整える必要があります。先進的にリスキリングを行っている海外の事例に学ぶことで、従業員にリスキリングの最新情報や重要さを発信し続けることも有効です。また、リスキリングのメリットを個人レベルで具体的に落とし込み、従業員が企業内で「価値を生み続ける人材」として生き残っていくために何が必要かを明確化することも重要です。それによって企業としてだけでなく、従業員個人としても成長・変化することへ意欲的になり、組織の中で新しいスキルや知識を生む文化ができ上がっていきます。個人でも学習することを厭わない姿勢ができれば、リスキリングという取り組みにより協力的になるでしょう。
モチベーションが維持される仕組みを作る
リスキリングを進めいくうえで、抵抗感のある従業員やモチベーションを維持できない従業員に対する対応も重要です。公平な評価制度で背中を押し、スキル習得に対するインセンティブを用意するなど、従業員側のメリットを明確にしていきましょう。従業員が学習を通じて新しい業務で実践的に活躍し、リスキリングによって新しい能力や功績を得られるという実感を得る仕組みづくりがとても重要です。従業員同士が同じ目的意識を持ち、刺激しあうことで組織としてもリスキリングに対する抵抗感は薄くなり、継続的な変革に対応できる強固な組織づくりが可能になるでしょう。
適した教育プログラムを選ぶ
企業として、どのように適したリスキリングの教育プログラムを用意するかも重要なポイントです。企業内のコンテンツを使用し、内製化にこだわってしまうケースも少なくありません。しかし、外部の教育プログラムやプラットフォーマー教育制度など、社外の専門家にアドバイスを求めたり、活用したりすることも有効といえるでしょう。
質のいいコンテンツだったとしても、それぞれの企業内課題と必ずしもマッチするとは限りません。あくまでも社内のリスキリングの取り組みにマッチする教育プログラムを選ぶことが、リスキリングを進めていくうえでとても重要な事項となります。
継続して実施する
リスキリングは継続して行うことが大切です。継続するために、社内理解や協力体制、モチベーションの維持やコンテンツ選びなど、企業が従業員に対して施す項目は多岐にわたります。しかし、従業員の学習に対する意識が促進され、効果が最大化する仕組みさえ構築することができれば、リスキリングの成果を企業内のキャリアパスなどに結合することもできるようになります。個人の人生戦略においても企業の経営戦略においても教育や学習といったステージは人生において何度も訪れます。リスキリングの経験が「学び続ける文化」を生み、企業にとっても従業員にとっても社会の急激な変化にも柔軟に対応する大きな力となると言えるでしょう。
リスキリング実行が企業と従業員の行き残り戦略
デジタル化が急速に進む現代において、変化の激しい時代への適応力が求められています。AIが担う業務も増える中、新しく生まれる業務もあります。多くの企業が人材不足という課題を前にして、既存の従業員の活躍の幅をリスキリングによってどう広げ、新しいものをいかに積極的に取り入れていくかで新たな価値創造の方法を模索していく必要があります。海外と比べると日本企業ではリスキリングの認知も推進もまだ進んでいませんが、リスキリングをいかに精度高く実行していくかが、今後の企業・従業員双方にとっての生き残り戦略と言えるでしょう。