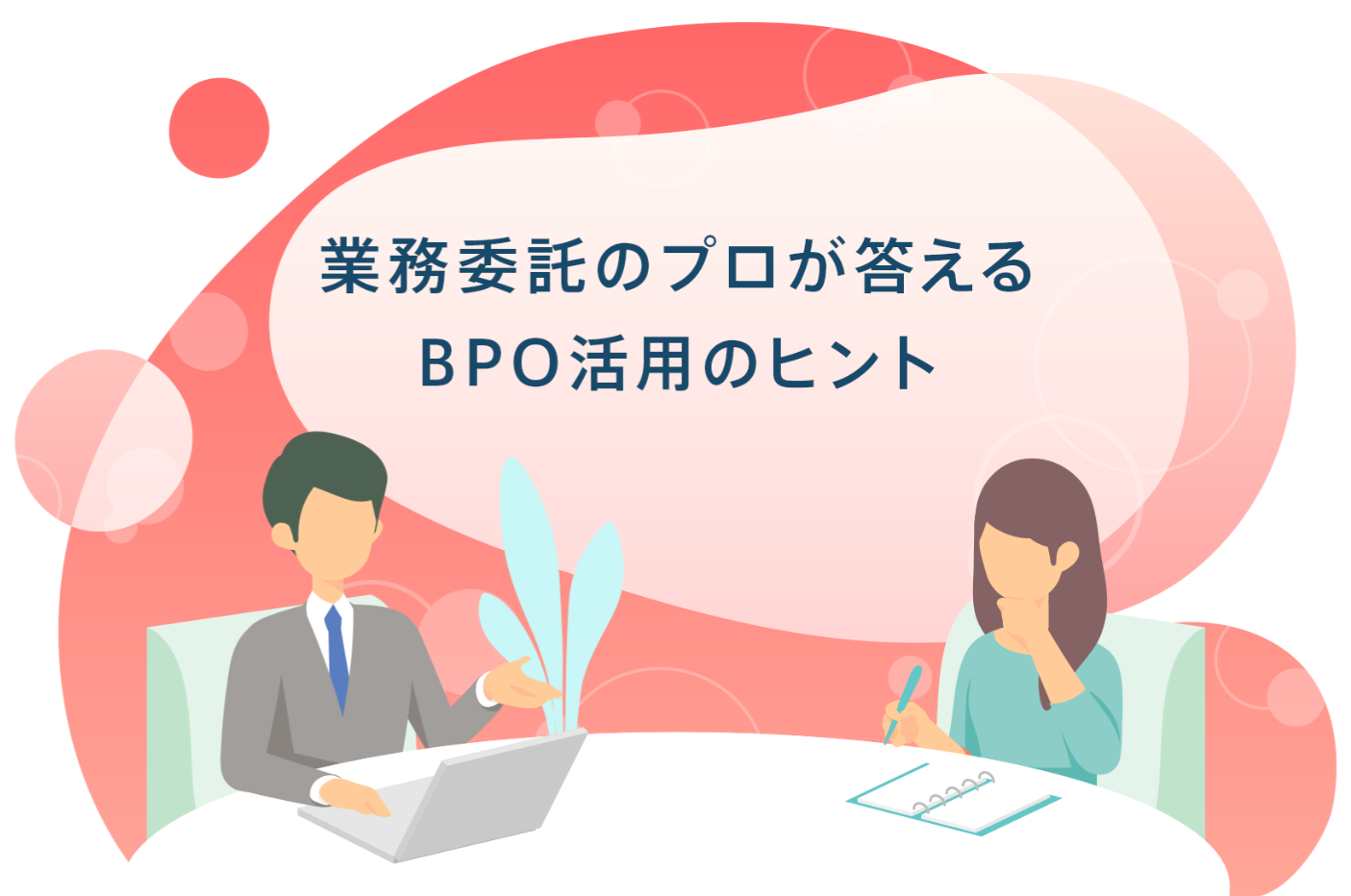BPRとは|メリットや注意点、進める手順を解説
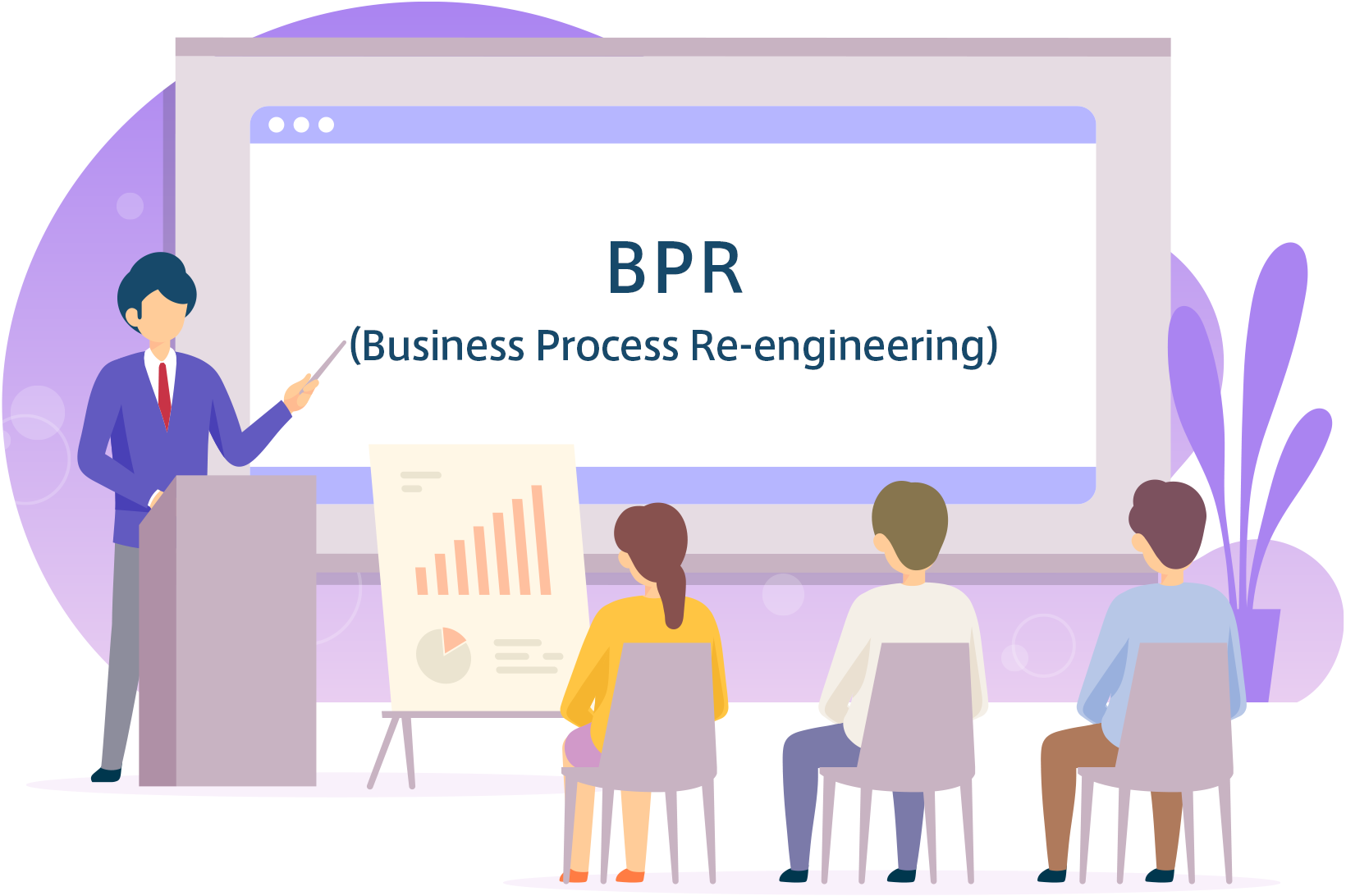
BPRは、既存のビジネスプロセスを根本的に見直し、抜本的に再設計することで、業務効率化や生産性向上を目指す手法です。1990年代に登場した概念ですが、人手不足や働き方改革、政府のDXの推進などを背景に、再び注目が集まっています。 この記事では、BPRが注目される背景や取り組むメリットのほか、取り組む上での注意点と具体的な進め方などについて解説します。
BPRとは
BPR(Business Process Re-engineering)は、日本語で「業務改革」と訳され、ビジネスプロセスを根本的に見直し、業務フローや組織構造、情報システムなどを再構築(リエンジニアリング)する手法を指します。
BPRは、元マサチューセッツ工科大学教授のマイケル・ハマー氏と経営コンサルタントのジェームス・チャンピー氏が1993年に出版した『リエンジニアリング革命』によって、世界的に広まったとされています。日本でも、バブル崩壊後の不景気を立て直す手法として注目されましたが、当時は一過性の話題となり、浸透することはありませんでした。
BPRが注目される背景
BRPが再び注目されている背景には、少子高齢化による人手不足や働き方改革の影響など、社会構造の変化があります。
企業が競争力を維持するためには、限られた労働力で生産性を向上させる必要があり、これまでの環境を刷新しなければなりません。また、時間や場所にとらわれない新しい働き方を実現するためには、既存のビジネスプロセスでは対応が難しくなり、変革が必要とされています。
数年前から経済産業省が企業のDXを推進しており、その点もBPRが注目される理由でしょう。
BPRと業務改善の違い
BPRと業務改善は、いずれも業務の効率化を目指すものですが、方法が異なります。
業務改善は、既存のビジネスプロセスをベースに、一部を修正したり改善したりすることです。それに対しBPRは、業務全体を見直し、ビジネスプロセスを再構築する改革を指します。業務改善は一部の部署のみでの取り組みですが、BPRは部署の垣根を越えて、全社で取り組む大掛かりな取り組みになるでしょう。
BPRとDXの違い
BPRとDX(Digital Transformation)の違いは、変革の対象にあります。
DXは単なるIT化とは違い、デジタル技術を利用して新しいビジネスモデルを創造することです。BPRがビジネスプロセスを改革するのに対し、DXが改革するのはビジネスモデルそのものといった違いがあります。
新しいビジネスモデルを創造するにあたって、既存のビジネスモデルのままでは効率化にはつながらないでしょう。DXを推進する過程でBPRは避けて通れないことであり、DX推進の中核といえます。
BPRを理解するためのキーワード
BPRが知られるきっかけとなった『リエンジニアリング革命』では、BPRの定義を「コスト、品質、サービス、スピードのような、重大で現代的なパフォーマンス基準を劇的に改善するために、ビジネスプロセスを根本的に考え直し、抜本的にそれをデザインし直すこと」としています。
BPRに取り組む際には、この中に含まれる4つのキーワードを意識することが重要です。
根本的
BPRでは、ビジネスプロセスの目的や内容を、ゼロベースで問い直します。単なる部分的な改善ではなく、「なぜこのプロセスが必要なのか?」を根本から見直すことが求められます。
抜本的
BPRでは、抜本的な再設計をおこなうことで、業務全体を大きく変えることを目指します。従来のやり方にとらわれず、新しいプロセスを大胆に導入する姿勢が重要です。
劇的
BPRの目的は、業務効率や成果を劇的に向上させることです。小さな改善ではなく、全社的な変革を通じて大きな成果を得ることを目指します。
プロセス
BPRの対象は、単なる業務単位ではなく、プロセスそのものです。業務を一連の流れとして捉え、その中で価値を生まない部分を排除し、付加価値を最大化することが目的です。
BPRに取り組むメリット
BPRを導入することで、企業では業務効率化や従業員満足度の向上といった、多くのメリットが得られます。ここではBPRの具体的なメリットをご紹介します。
業務効率化と生産性向上
BPR実施にあたって業務フローを抜本的に見直すことで、無駄な手順や非効率的な工程を排除し、業務効率化や生産性向上を実現できます。
BPRをおこなう際は、既存の業務フローやプロセスを棚卸ししなければなりません。その過程では、現在の業務の「ムリ(無理)・ムラ(斑)・ムダ(無駄)」が可視化されます。それらをなくすビジネスプロセスを再構築することで、業務効率の向上が期待できるでしょう。
また、ムリ・ムラ・ムダを排除することで、人件費やシステム利用料、設備費など、さまざまなコストを削減可能です。経営資源をより重要な業務に投下できるようになり、生産性向上にもつながります。
従業員の満足度向上と意識改革
全体最適が図られ、非効率な業務フローやルールをなくすことで、従業員の負担を軽減できます。労働時間の短縮やコア業務への集中が可能になり、仕事へのモチベーションや組織へのエンゲージメントを高められるでしょう。従業員満足度の向上は業務品質の向上につながり、顧客満足度の向上も期待できます。
BPRを進めるためには、上層部だけではなく、従業員も巻き込んでいかなければなりません。ヒアリングしたり議論したりする過程で、BPRや企業としての目標達成の重要性の理解が高まり、従業員の業務に対する意識改革が期待できます。
スピーディーな意思決定
BPRに取り組むことは、迅速な意思決定にもつながります。経営の意思決定には現状把握や課題分析といった過程が必要ですが、BPRを通じて既存の業務全体を見直すことで、何が意思決定のボトルネックなのかを可視化できます。問題点や改善ポイントを発見して対処していくことで、スピーディーな意思決定が可能になるでしょう。
リスクマネジメントの強化
BPRに取り組むことで、業務フローの見直しやマニュアル化を進めることができ、属人化の解消が可能です。業務の属人化は、品質管理の困難やブラックボックス化による効率低下を招き、担当従業員の移動や退職があれば、業務の継続が困難になるリスクもはらんでいます。
BPRでビジネスプロセスを再構築することで、属人化のリスクを回避して、安定的な業務遂行ができるでしょう。
BPRに取り組む際の注意点
BPRには多くのメリットがありますが、実施する際には従業員の理解を得たり、工数とコストを検討して置いたりといった注意点があります。これらを理解し、適切に対処することで失敗を防ぎ、成功率を高めることができます。
従業員と経営層の摩擦
ビジネスプロセスの見直しや組織改革は、従業員にとってこれまでの方法を変えることになり、負担や不安を伴うかもしれません。既存の業務の進め方に固執したり、新しい方法になじめなかったりする従業員が出てくる可能性があります。BPRを推進する過程で、業務時間を圧迫されることに不満を持つこともあるでしょう。
BPRに取り組む際は、意義や目的を十分に説明し、従業員とのコミュニケーションを通じて合意形成を図ることが重要です。
工数とコストの増大
BPRでビジネスプロセスを見直すためには、現状の業務フローや組織体制も見直さなければなりません。その過程では多くの工数がかかり、通常の業務にも影響する可能性があります。
また、新システムや設備の導入が必要になり、そのコストはもちろん、運用するための知識やスキルを持った人材も必要になる可能性もあるでしょう。計画段階で慎重に予算や規模、優先度などを検討しておかなければなりません。
経営層の関与不足
BPRは全社的な取り組みであるため、経営層の強いリーダーシップが求められます。取り組みが現場任せになると、遅滞や混乱が生じたり、期待した効果が得られなかったりする可能性があります。
BPRは企業の競争力を高めるための手段であるからこそ、経営層と従業員が一丸となって取り組まなければなりません。全体を見渡せるポジションである経営層が積極的に関与し、改革を進めていきましょう。
BPRを進める手順
BPRに取り組むためには、大きく5つのステップがあります。BPRは、企業に大きな変革をもたらす取り組みです。段階を踏んで着実に進めていきましょう。
1. 検討
まずは、BPRの目的を明確にし、それに沿って目標を設定します。目的を明確にするためには、現状の課題を洗い出さなければなりません。立場によって見える課題は異なるため、階層の異なる従業員から幅広く改善すべき点をヒアリングすることが重要です。
ヒアリング後は企業戦略を踏まえたうえで、従業員代表や役員を交えて議論を重ね、できるだけ具体的な目的・目標を設定しましょう。
目的と目標を明らかにしたら、対象となる業務の範囲も明確にしましょう。対象が明確でないと、取り組みもあいまいになります。BPRで重点的に改革すべきプロセスも、この段階で決めておきます。
2. 分析
ヒアリングした課題に対し、分析して改善する方法を検討します。各業務フローの内容や問題点、非効率な部分を特定し、可視化することが重要です。
分析に利用するフレームワークはいくつかありますが、BPRでは下記の2つがよく利用されます。
ABC(Activity Based Costing)
ABCは、間接費を明らかにする原価計算の手法です。「活動基準原価計算」ともいわれ、ビジネスプロセスを活動(Activity)単位に分類し、それぞれのコストを算出できます。活動単位でかかるコストを把握することで、不要なコストの削減につなげられます。
BSC(Balanced Scorecard)
BSCは、企業の戦略やビジョンを「財務」「顧客」「ビジネスプロセス」「学習と育成」の4つの観点から評価する方法です。コストのみでは判断しにくい業務を評価し、多面的に課題を発見することに役立ちます。
3. 設計
課題を分析した結果から、実際のビジネスプロセスを再設計するための戦略や方針を策定していきます。戦略や方針を決めたら、それに従って、具体的にどのような手法をどのプロセスで適用すべきか検討しましょう。
この段階で、部門によって異なる業務フローや、システムの標準化についても検討します。限られた時間で課題を解決するために、優先順位をつけることが重要です。
BPRは社内全体に影響を与えるため、全員が共通認識を持って推進しなければなりません。各部門で目標や目的を共有しつつ、連携しながらビジネスプロセスを再設計します。
4. 実施
設計したビジネスプロセスを、実際の業務に適用します。スムーズに進めるためにも、社内全体が共通意識を持っていることが重要です。実施する前には、経営層からBPRの目的や必要性をあらためて説明し、従業員がBPRを自分事として考えられるようにしましょう。
BPRは業務を「改革」することであるため、簡単に完了するものではありません。新たなビジネスプロセスの浸透にも時間がかかるため、最終的なゴールのほかに、短期的なスモールゴールを設け、進捗を確認します。
5. 評価
再設計したビジネスプロセスを評価し、目標に対する成果を測定します。新たなビジネスプロセスが機能しているか、以前のビジネスプロセスと比較して、どのような効果があるかなどを測定しましょう。
問題が起きている場合はその理由を特定し、再度「検討」のステップに戻って修正をおこないます。
BPRを推進するための手法
BPRを成功させるには、BPRの目的や企業の課題に応じて、適切な手法を活用することが重要です。ERPやシェアードサービス、BPOなどから、自社に合った手法を組み合わせてBPRを進めましょう。
ERP
ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業の主要な業務プロセスを統合的に管理するためのシステムや手法のことを指し、「企業資源計画」とも訳されます。
部門間で分断されがちな情報を一元管理し、データの重複や手作業を削減し、業務フローをスムーズにする効果があります。複数のシステムを統合することで、ITコストの削減が期待でき、情報が可視化されることで迅速な経営の意思決定を実現します。
シェアードサービス
シェアードサービスとは、グループ企業や支店間の間接業務を集約し、専用の部門や子会社で一括して管理・運営する仕組みを指します。
業務の標準化や効率化を通じて、コスト削減や品質向上を図ることが目的であり、リソースの有効活用やコア業務への集中といった効果が期待されます。
BPO
BPO(Business Process Outsourcing)は、特定の業務プロセスを外部の専門業者に委託する手法です。高度な専門知識を持つ外部リソースを活用することで、自社はコア業務に注力し、業務効率化やコストの削減が図れます。
BPOは、業務効率化やコスト削減を目的に、特定の業務を委託する点でシェアードサービスと似ていますが、外部企業に業務を委託する点が異なります。
BPRを導入して、業務効率を向上させよう
BPRは、既存のビジネスプロセスを根本的に見直し、抜本的に再設計することで、業務効率化や生産性向上を図る手法です。人手不足が深刻化し、DX推進や働き方改革が求められる現代において、BPRは再び注目されるようになりました。
BPRを進める際には、従業員の負担や導入コストを考慮し、段階的に進めることが大切です。成功のカギは、目的を明確にし、継続的にプロセスを評価・改善していくことにあります。BPRを効果的に活用し、企業の競争力を高めていきましょう。