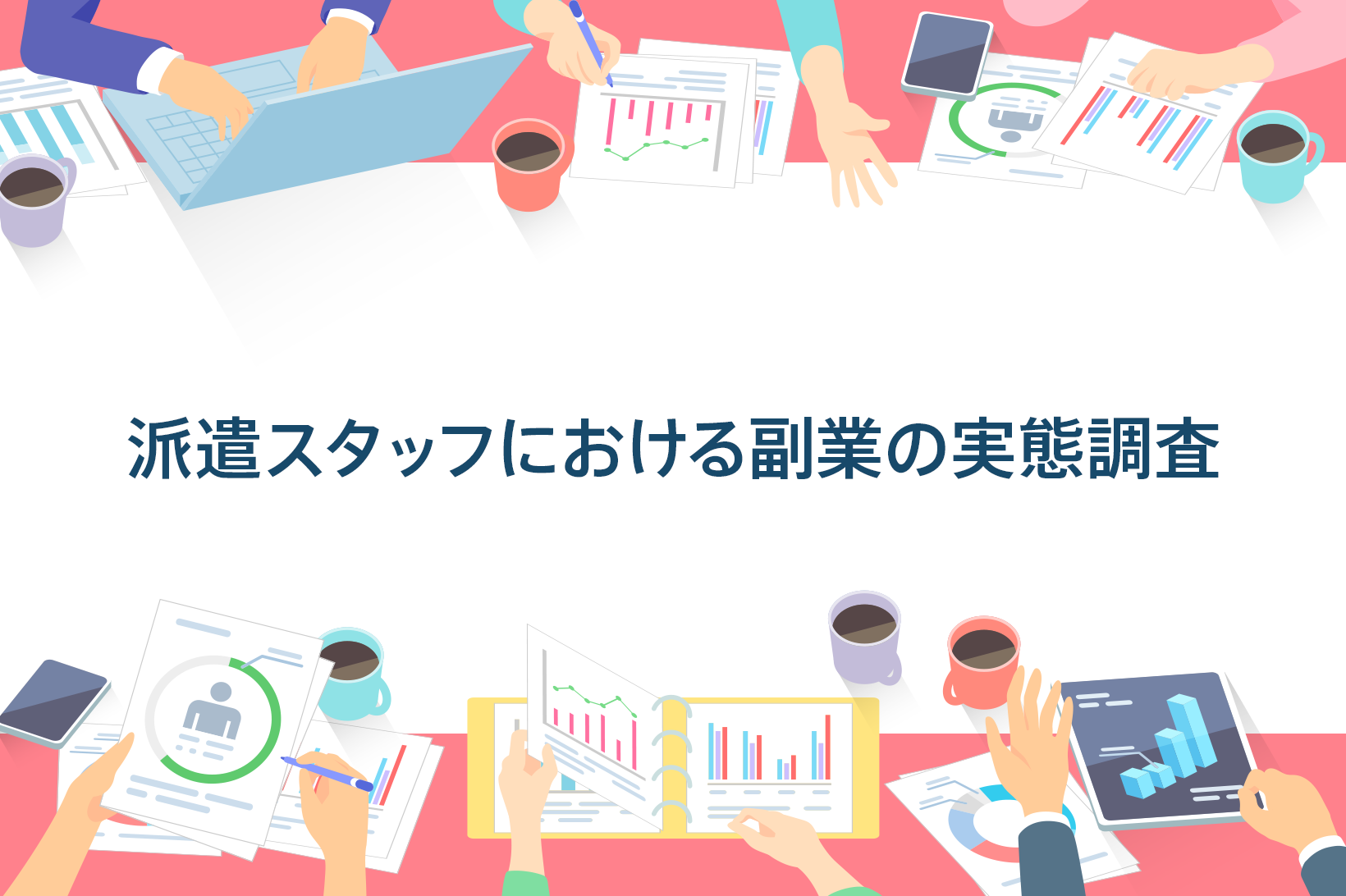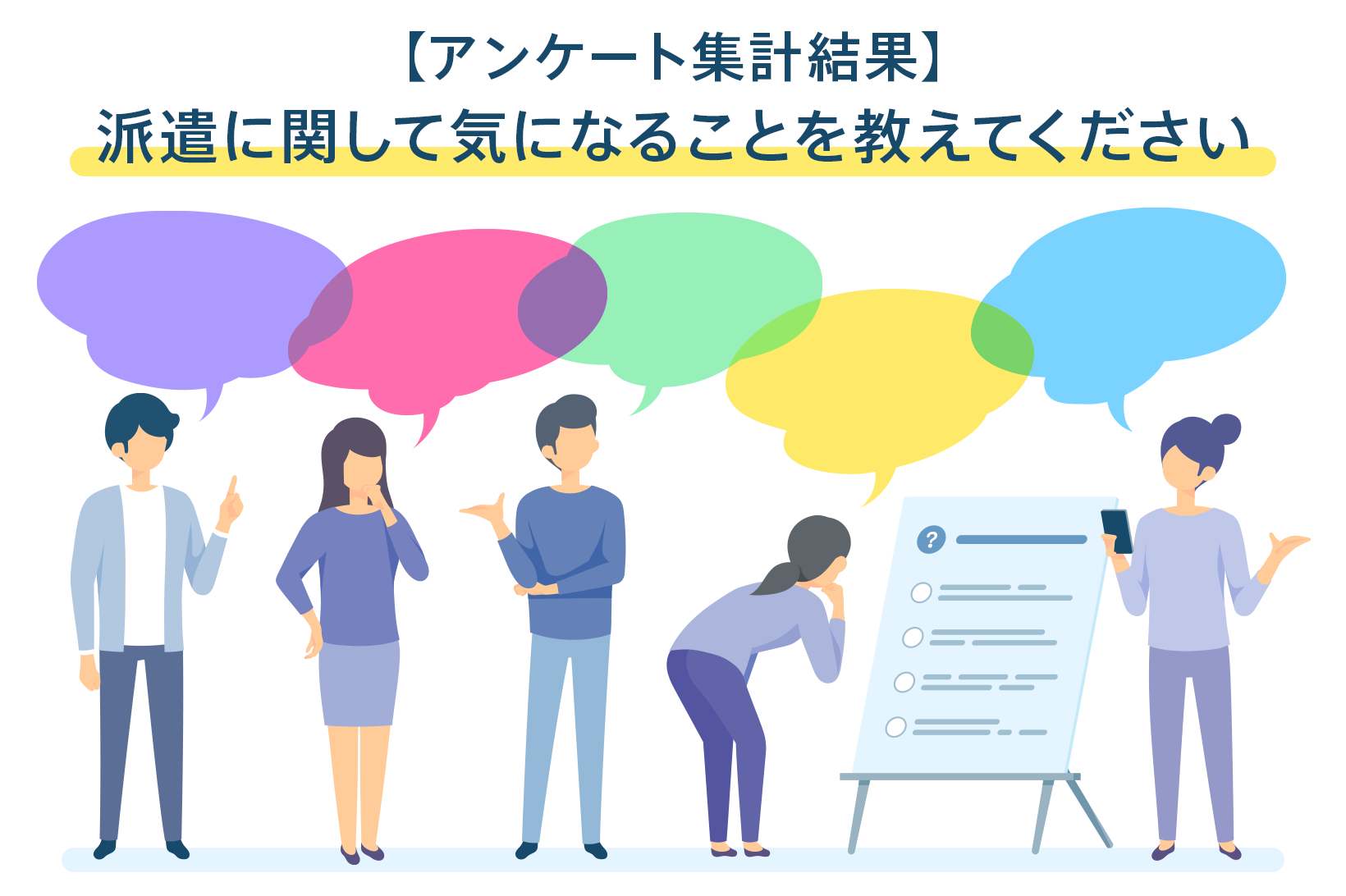スキルと専門性重視の「ジョブ型雇用」|特徴とメリット・デメリット

終身雇用や年功序列が根付いていた日本社会に、さまざまな変化が現れています。そのうちのひとつが、大企業を中心に導入が進んでいる「ジョブ型雇用」です。「メンバーシップ型雇用」といわれる日本の一般的な雇用制度とはどう違うのでしょうか。「ジョブ型雇用」の特徴と企業にとってのメリット・デメリットをご紹介します。
目次
「ジョブ型雇用」とは
「職務内容に合った人を採用、評価する」雇用形態
「ジョブ型雇用」とは、仕事内容および範囲を明確に定義したうえで、その要件に合った人材を採用し、定義にそった成果で評価をおこなう雇用形態です。「仕事に対して人を割り当てる」という考え方で、人材採用にあたっては「職務内容に必要なスキルがあるか」が重視され、より専門性を高める目的で採用がおこなわれることになります。
欧米諸国を中心に海外では、新卒・中途採用いずれにおいても「ジョブ型雇用」が一般的です。一方、日本では中途採用において「ジョブ型雇用」に近いかたちが見られます。たとえば、急に専門職の人が退職してしまい、同じようなスキル・資格を持った人材を中途採用する場合や、新規事業のために外部からスペシャリストを求める場合などです。
「ジョブ型雇用」の特徴|重視するのはスキルと専門性
「ジョブ型雇用」では、職務内容の詳細を「職務記述書(ジョブディスクリプション)」に明記したうえで、企業と働く人が雇用契約を結びます。そのため、採用にあたっては職務の目的や目標、責任と権限の範囲、必要な知識・スキル・経験・資格などを細かく定める必要があります。
採用時に重視されるのは、年齢や学歴、意欲より、顕在化されたスキルと専門性です。入社時にすでに会社が求めるスキルを身につけていることが前提になるので、入社後の一括研修などは実施されないことが多く、各自が自己研鑽でより専門性を高めていく姿勢が求められます。
「ジョブ型雇用」と対比される「メンバーシップ型雇用」とは
「ポテンシャル重視、育成を前提とした」雇用形態
日本で長年主流とされていたのは「メンバーシップ型雇用」で、「ジョブ型雇用」と対比される雇用形態です。
「メンバーシップ型雇用」では「人に仕事を割り当てる」という考え方が基本で、就業経験のない新卒者のポテンシャルを重視して採用し、終身雇用を前提に研修とジョブローテーションによって人材育成をしていきます。
メンバーシップ型雇用の特徴|入社後に適性を見出す
「メンバーシップ型雇用」では、終身雇用を前提として勤続年数に応じて給与が上がったり昇給したりする「年功序列」が一般的です。企業にとっては長期的な視点で人材育成ができ、雇用が安定するメリットがあります。また業務範囲を明確にして雇用契約を結ぶわけではないので、会社の都合による職務変更や転勤などの配置転換がしやすいといえます。
一方、働く人にとっては、入社後の研修やジョブローテーションを通じて自分の適性を見出したり、キャリアプランを考えたりすることができます。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは企業によって異なりますが、一般的に見られる傾向をご紹介します。
| ジョブ型雇用の傾向 | メンバーシップ型雇用の傾向 | |
| 基本的な考え方 | 仕事に人を割り当てる | 人に仕事を割り当てる |
| 採用方法 | 中途採用・経験者採用 | 新卒採用 |
| 採用タイミング | 随時・通年・欠員発生時・新規事業 | 特定の時期に一括採用 |
| 教育・研修 | 自発的に研鑽 | 企業が提供する研修やジョブローテーション |
| 仕事内容 | 専門的、限定的 ※職務記述書の記載内容に基づく | 総合的、全般的、非限定的 |
| 労働時間 | 働き手が裁量で決める | 企業が一律で決める |
| 相性のよい働き手の志向 | スペシャリスト | ゼネラリスト |
| 報酬 | 成果で決まる | 勤続年数や等級・役職で決まる |
| 人材の流動性 | 高い | 低い |
採用方法の違い
「ジョブ型雇用」は必要なときに必要な人材を採用するのが通例で、プロジェクトや案件ベースでの有期雇用が多い傾向にあります。「メンバーシップ型雇用」では、無期雇用を前提として毎年4月入社の新卒者を一括採用するのが一般的です。
仕事内容の違い
「ジョブ型雇用」では、職務記述書に記載されている専門的かつ限定的業務を担当し、いつどのように遂行していくかは、働き手の判断に委ねられています。それに対し「メンバーシップ型雇用」では、企業の方針・計画により職務内容や勤務地、労働時間などを各人に割り当てていきます。結果的にゼネラリスト(幅広い分野で知識・スキルを身につけ、オールマイティに対応できる人)が育成されやすい環境といえます。
報酬・待遇の違い
「ジョブ型雇用」は職務記述書に明記された職務に対する成果が評価の基準となり、それに応じた報酬が約束されます。一方、「メンバーシップ型雇用」では社歴と職級に応じて昇給・昇進を決める「年功序列」がベースとなります。しかしながら、日本でも近年の雇用の多様化に伴い、メンバーシップ型雇用であっても「成果報酬」という考え方を取り入れる企業も出てきています。
「ジョブ型雇用」における企業のメリット・デメリット
「必要なときに必要な人材を」という観点から、ジョブ型雇用では雇用後のミスマッチが起こりにくく即戦力になるといったメリットがある一方で、なかなか求める人材に巡り会えなかったり条件が合わなかったりといった難しさもあります。
「ジョブ型雇用」で期待される企業のメリット
求める人材を効率よく確保できる
仕事に必要な経験やスキルを持った人材を、必要なときに募集・採用するので、効率的に人員の適正化が図れます。入社後に一から仕事に必要な知識や技術を教育する必要がなく、即戦力として活躍してもらえるのは企業にとって大きなメリットといえるでしょう。
雇用のミスマッチを防ぐ
職務内容や責任の範囲などを明確に規定したうえで雇用契約を結ぶので、採用においてミスマッチが起こりにくくなります。また職務記述書で報酬につながる評価基準が明確になっているので、企業は報酬設計がしやすく、従業員も報酬に対する納得感が得られやすいようです。
スペシャリストを育成しやすい
はじめから専門分野に特化した人材を採用するため、入社後に研鑽を積んでもらうことによって、さらに高いレベルのスペシャリストへの成長が期待できます。入社後に適性を見極めながら専門性を育てていくより、スピーディかつ確実にスペシャリストを育成しやすいといえます。
「ジョブ型雇用」で考えられる企業のデメリット
採用難易度が高くなる可能性がある
日本ではまだ専門分野の仕事に特化したスペシャリストが少ないのが実情ですが、高レベルのスペシャリストを欲している企業は多く、競争率の高い採用になります。また、募集前に職務内容を細部まで設定して明記する必要があるため、人事側のスキルや手間も求められます。
契約範囲外の仕事を依頼できない
雇用契約を結ぶ際に提示した職務記述書に記載されている仕事以外は、依頼することが難しくなります。ほかの部署や職種への配置転換や転勤も同様です。本人が自らの意志で職務記述書に記載されていない仕事、たとえば同僚の仕事を手伝うという行為も、契約違反になってしまう可能性があるので、「ジョブ型雇用」を導入する際には注意が必要です。
チームワークを醸成しにくい
ジョブ型雇用では個人の業務範囲が明確で、それぞれの業務に集中することになるため、横とのつながりが生まれにくいといった傾向があります。全体像が見えないことやコミュニケーションロスがストレスやモチベーションの低下につながれば、パフォーマンスにも支障が出てしまいます。情報共有の場や仕組みをつくるなど、安心して個々の業務に集中できるような環境づくりなどが大切です。
まとめ
働き方の多様化が進み、国際的な競争も激化するなかで注目されている「ジョブ型雇用」。海外で主流とはいえ、日本ではまだ労働市場が成熟しているとはいえない状況です。日本企業が「ジョブ型雇用」のメリットを得るためには、長く根付いてきた人材採用・育成の考え方や評価の仕組みなどを進化させていく必要があるといわれています。海外の「ジョブ型雇用」をそのまま転用するのではなく、日本社会に合ったかたちに変換して取り入れていくことが期待されています。